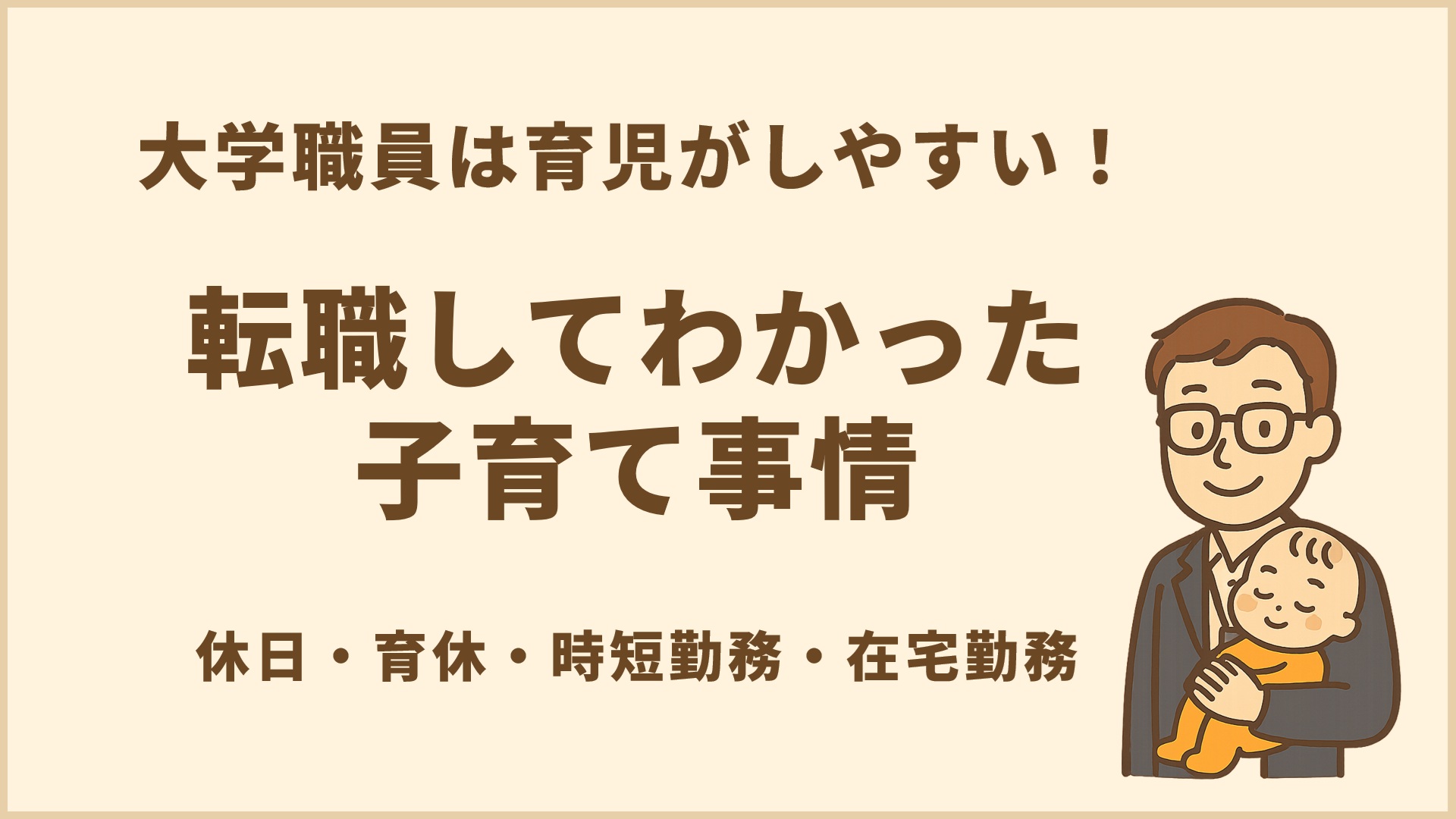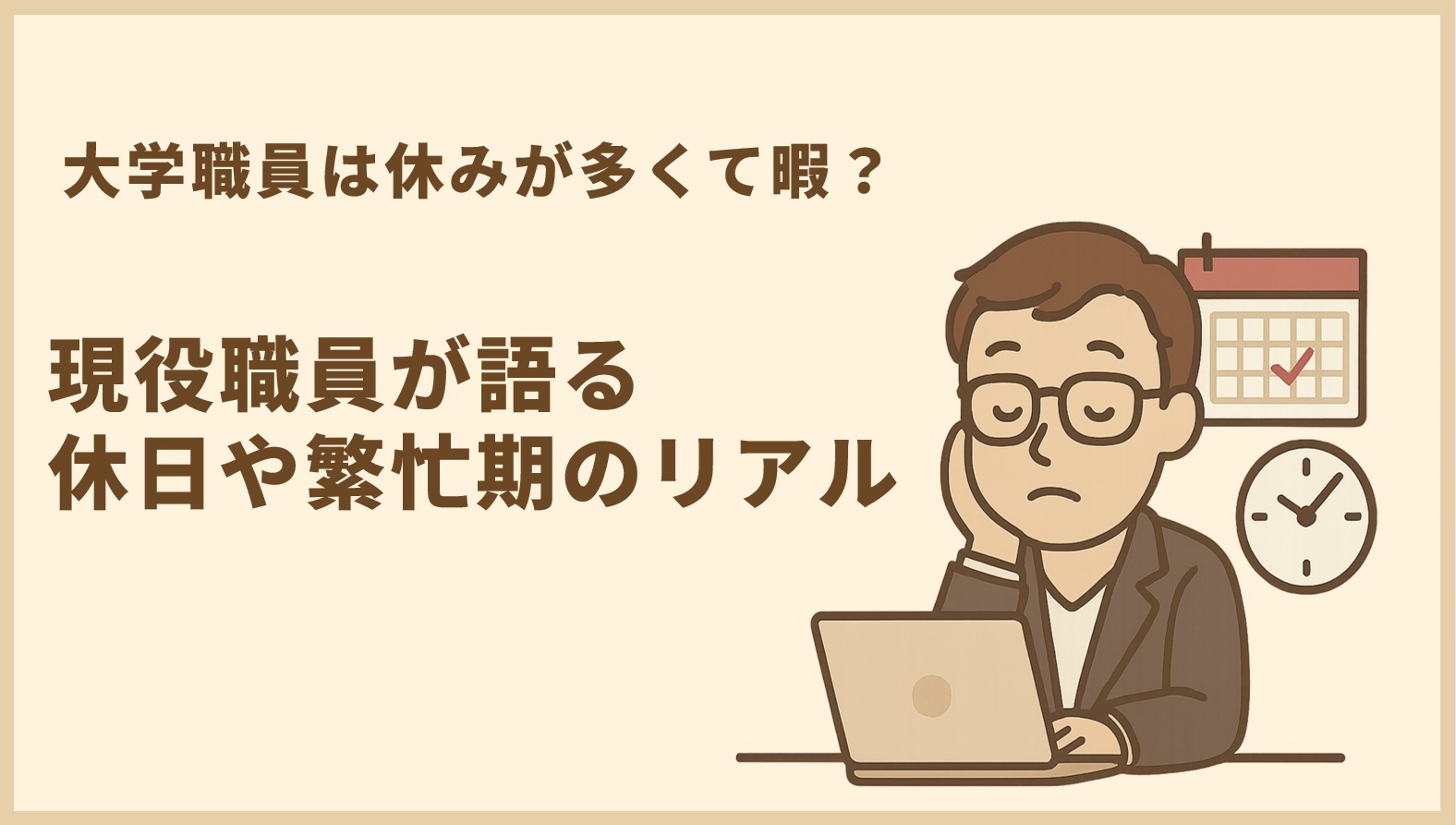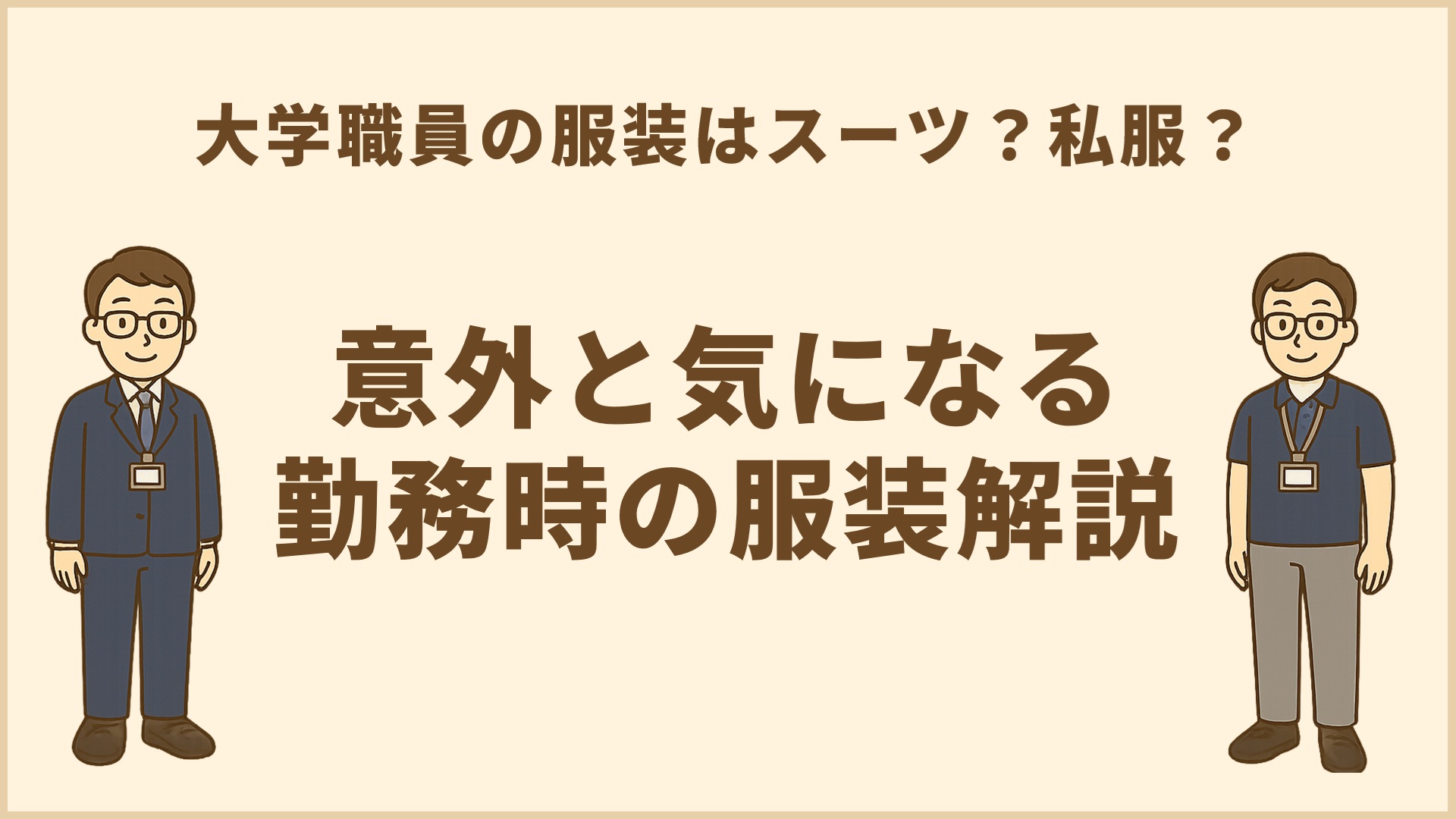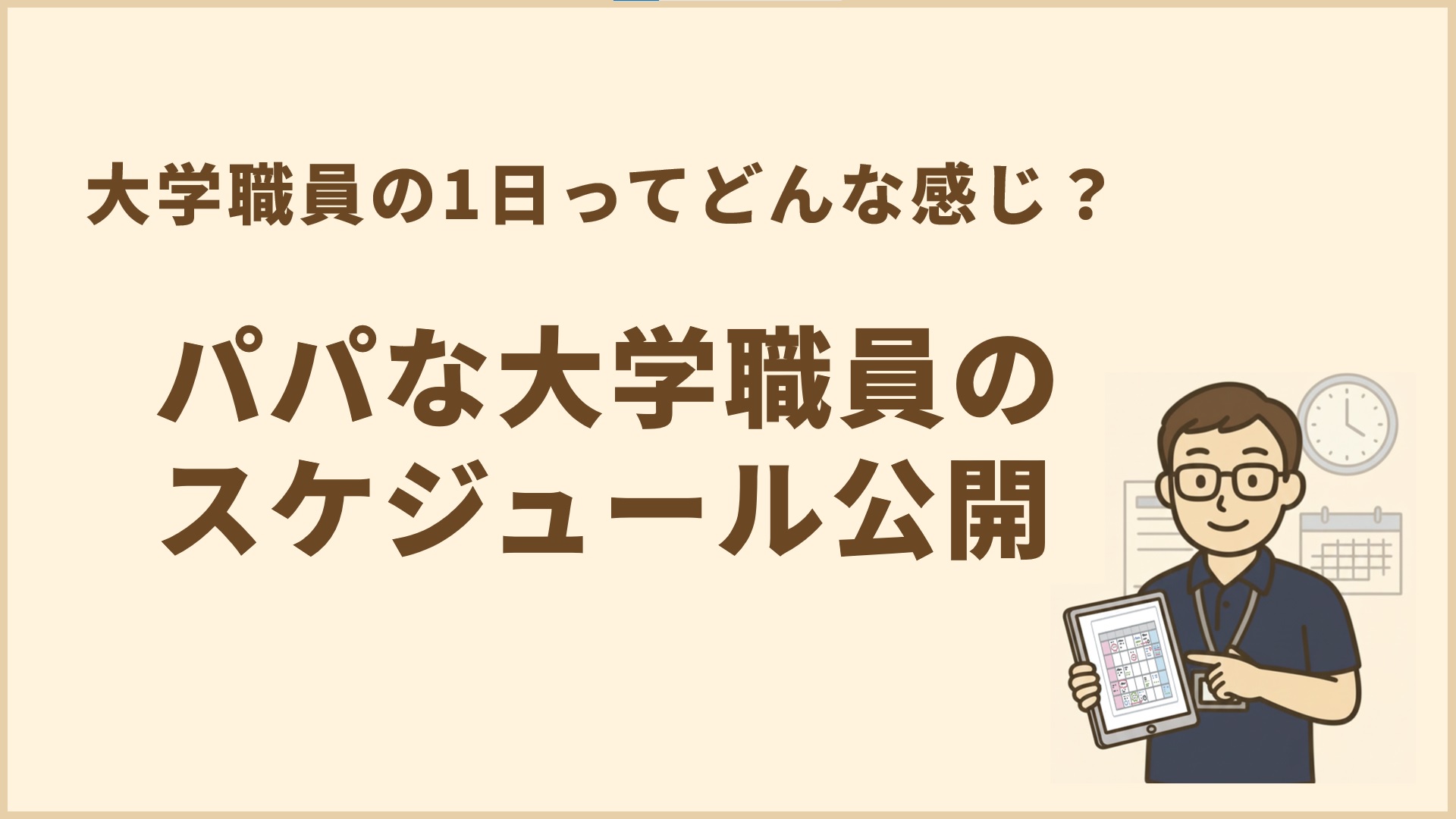大学職員は育児がしやすい!転職してわかった子育て事情|休日・育休・時短勤務・在宅勤務まで解説
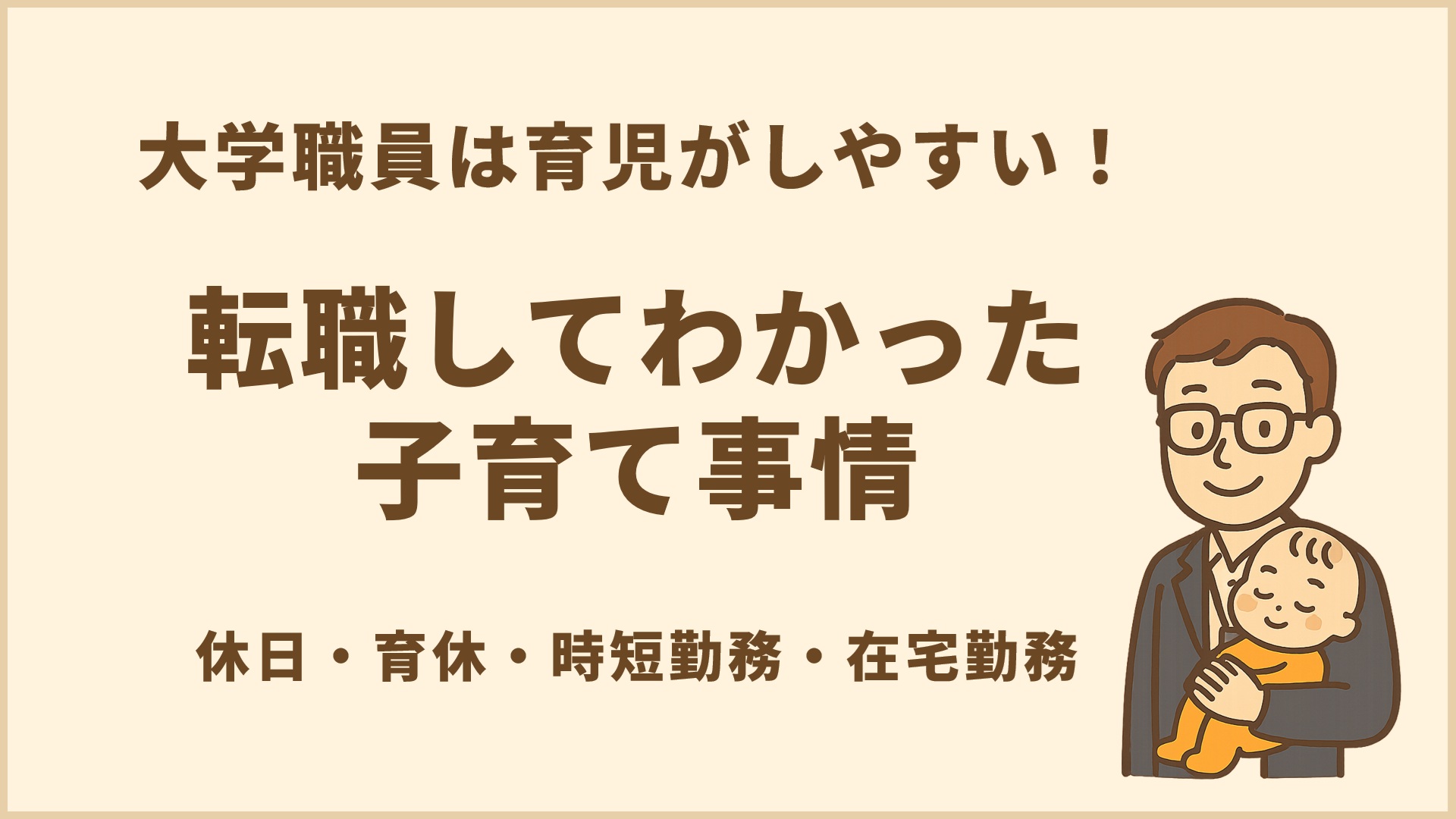
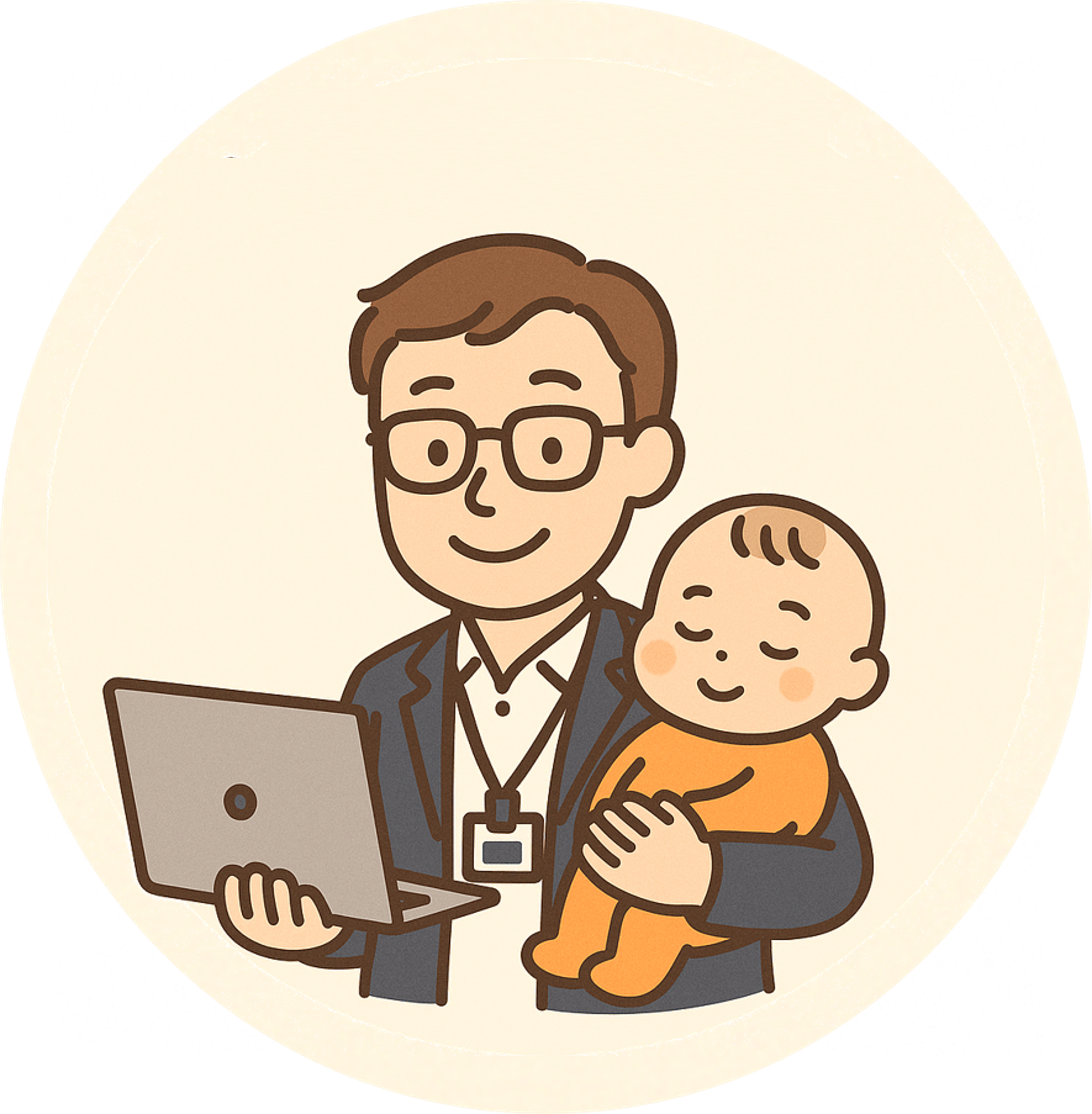
「子育てと仕事を両立できる職場がいい」
特に子育て世代の方が転職を考える際、きっかけとなる大きなポイントのではないでしょうか。私自身、子育てと仕事の両立を考えて大学職員に転職しました。
実際に大学職員に転職した結果、強く感じたのは、大学職員は育児との相性がかなり良いということです。もちろん部署や大学によって差はありますが、「制度が整っている&使いやすい」印象があります。
今回は、これから大学職員を目指す人や、現在子育て中の方に向けて、休日・育休・時短勤務・在宅勤務(フレックスタイム含む)の4つに分けて、大学職員の育児事情を紹介します。
休日事情|大学職員は休みが取りやすい
まずは休日から。大学職員は基本的に土日休み+祝日休みがベースです。また、多くの大学で夏休みが10日前後ある点も魅力的です。ただし、大学のカレンダー(学事暦)に合わせて動くため祝日が勤務日になるケースは見受けられます。その他、土日の出勤や繁忙期との兼ね合い等も含めて、年間スケジュールのイメージは以下の記事も併せて読んでみてください。
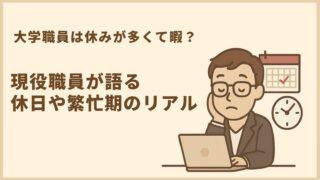
そのうえで、有給休暇等の休暇の取得についてですが、非常に休みを取りやすい環境だと私は感じています。多くの方が年20日支給される有給休暇をほぼ消化していて、よほど重要な業務の当日とかでなければ気軽に休みを取得しています。また、育児や介護が必要な方には追加の休暇を取得できる制度もあり、個々人の事情に合わせて柔軟に休みを調整できる環境や、それをお互いに認め合う風土が整っているなと感じます。私自身も、子どもが熱を出して急遽お休みすることがありますが、職場の方々には理解してもらえているなと実感しています。
育児的なメリット:
- 特に夏休みは長期休暇で子どもの夏休みに合わせやすい。
- 育児を理由に、まとまった休みを予定することも、突発的に休むこともできる。
育休事情|男性でも取りやすい雰囲気
次に育児休暇。大学職員の大きな特徴として、育休を取ることへの心理的ハードルが低い点があります。もちろん大学によっても異なるのだと思いますが、概ねどこも以下のような状況と思います。
- 制度上の育休期間:法律通り(原則1歳まで、条件付きで2歳まで)
- 取得率:女性はおそらく80%以上、男性もかなり増えてきている(大学毎に異なりますが、数字は公表されているので、気になる大学の)
- 職場の雰囲気:育休取得を歓迎する空気感がある
私自身の周囲でも、男性職員が数か月単位で育休を取るケースが増えています。特にここ数年は「男性の育児休暇は当たり前」という雰囲気になってきました。
育児的なメリット:
- 長期間しっかり休めるので、ママの負担を軽減できる。
- キャリア・給与への影響も少ないので、余計な心配なく育児に集中できる。
時短勤務事情|小学校入学まで柔軟に対応可能
次は時短勤務。民間企業等でも時短勤務は一般的になってきていると思いますが、大学職員でも子どもが小学校に入るまで時短勤務を使えるケースが多いです。私の職場では、概ねどこの部署にも時短勤務されている人がいらっしゃいます。
- 利用できる期間:多くは子どもが小学校入学まで
- 勤務時間の例:9:00~16:00、10:00~17:00 など
- 利用者の割合:女性が中心だが、男性の利用もじわじわ増えている(特にお子さんが1~2歳の時など)
育児的なメリット:
- 保育園の送迎や、急な発熱などにも対応しやすい。
- 職場の雰囲気も時短勤務に慣れているため、気まずさが少ない。
在宅勤務・フレックスタイム事情|コロナ以降の変化
最後に、在宅勤務とフレックスタイムについて。これは大学によって差が大きいですが、コロナ以降、大学においても制度を取り入れるところが増えてきている印象があります。
例えば私の大学では、
- 在宅勤務:週1~2日程度、理由とともに申請すればOK。子育てに関する理由についてはかなり柔軟に認められます。ちなみに大学職員の仕事は、比較的内向きの仕事が多いので、単発であれば自宅でも全然業務出来ます。
- フレックスタイム:導入されている大学はありますが、私の職場では未導入。ただし、事情に応じた時差出勤の制度はあるので「ちょっと明日は1時間ずらしで」みたいなことは可能です。多くの大学で、制度は違えど、少しずつ柔軟性の高い働き方ができるようになっています。
育児的なメリット:
- 子どもの事情に合わせて働ける。「早退→在宅勤務」のような柔軟な対応も。
- 週に1日でも通勤時間が減るだけで、体力的にかなりラク。
まとめ|大学職員は育児との両立がしやすい職場
大学職員は育児に関して「制度が整っている&利用しやすい」点が大きな強みです。
- 休日:休暇が取りやすく、夏休みのような長期休暇も。
- 育休:男性も取りやすく、キャリアへの影響が少ない。
- 時短勤務:多くの大学で当たり前のように利用可能。
- 在宅勤務・フレックス:コロナ以降で広がり、柔軟な働き方がしやすくなっている。
もちろん大学によって差はありますが、全体として子育て世代に優しい職場環境であるのは間違いないかと思います。実際、私自身、転職してから圧倒的に家族との時間が増えました。
これから転職を考えている方にとって、「育児のしやすさ」は大学職員の大きな魅力のひとつになると思います。今回の内容が参考になれば幸いです。
また、大学職員に興味がある方・転職を考えている方に向けて、転職の流れなどを示したロードマップの記事も用意しています。転職を考えている方は、こちらの記事も併せて読んでみてください。
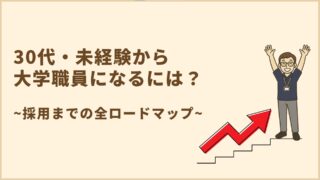
その他、大学職員の仕事内容や働き方に関する記事についても参考にしてみてください。