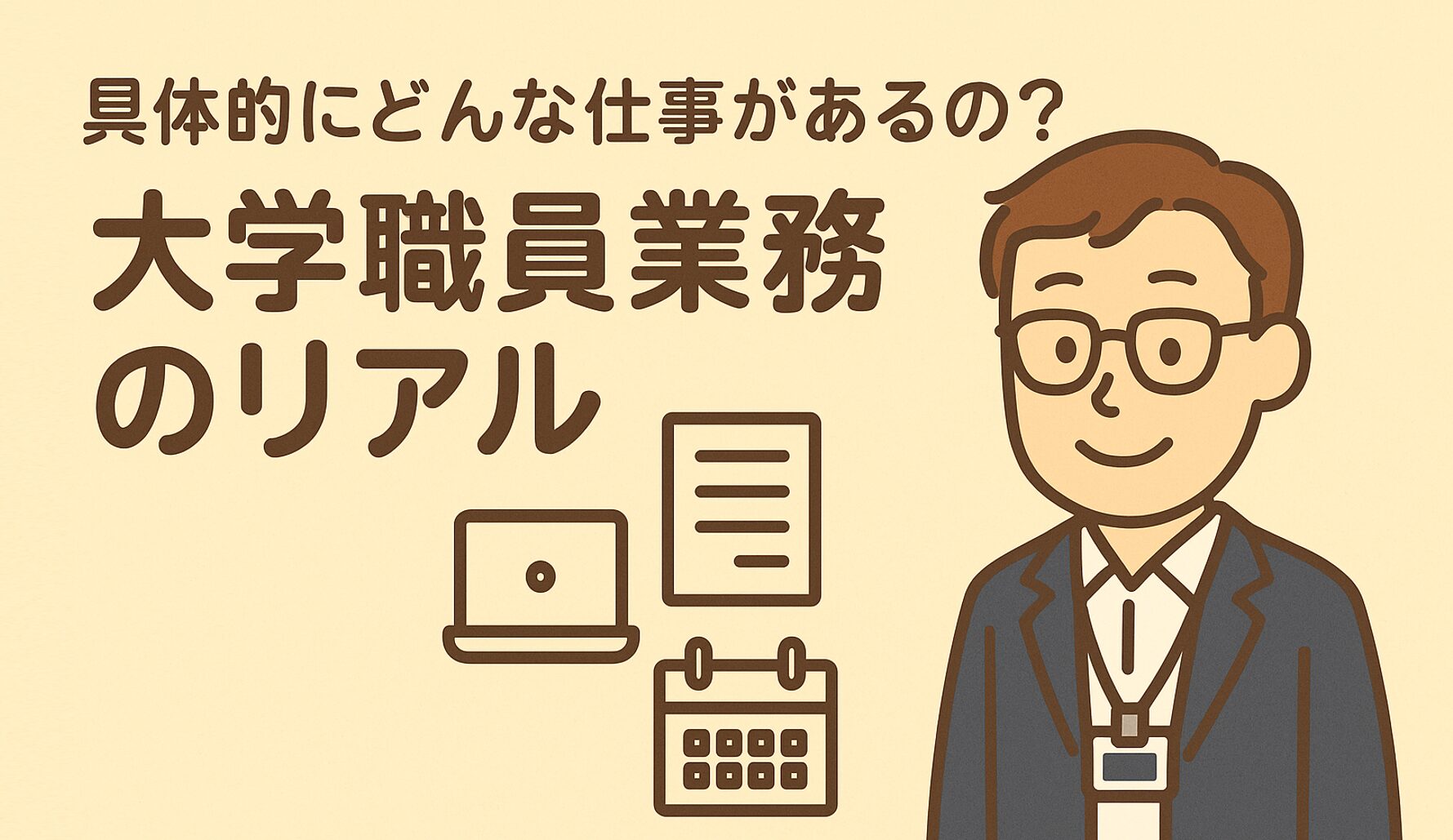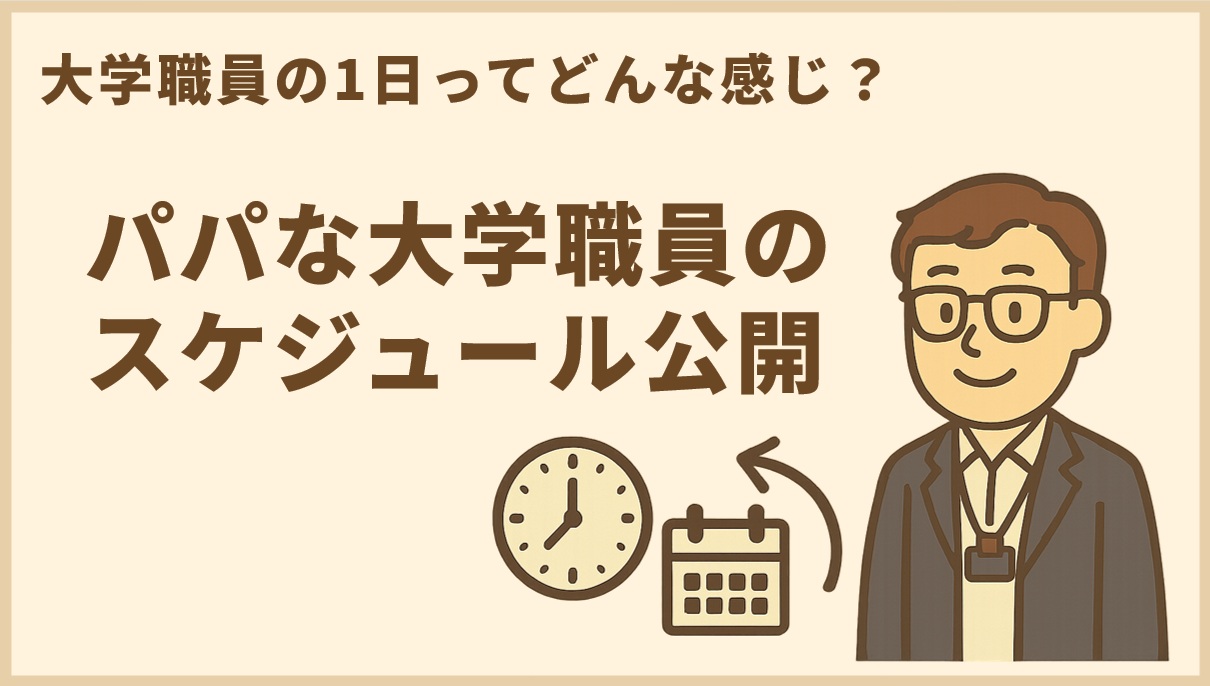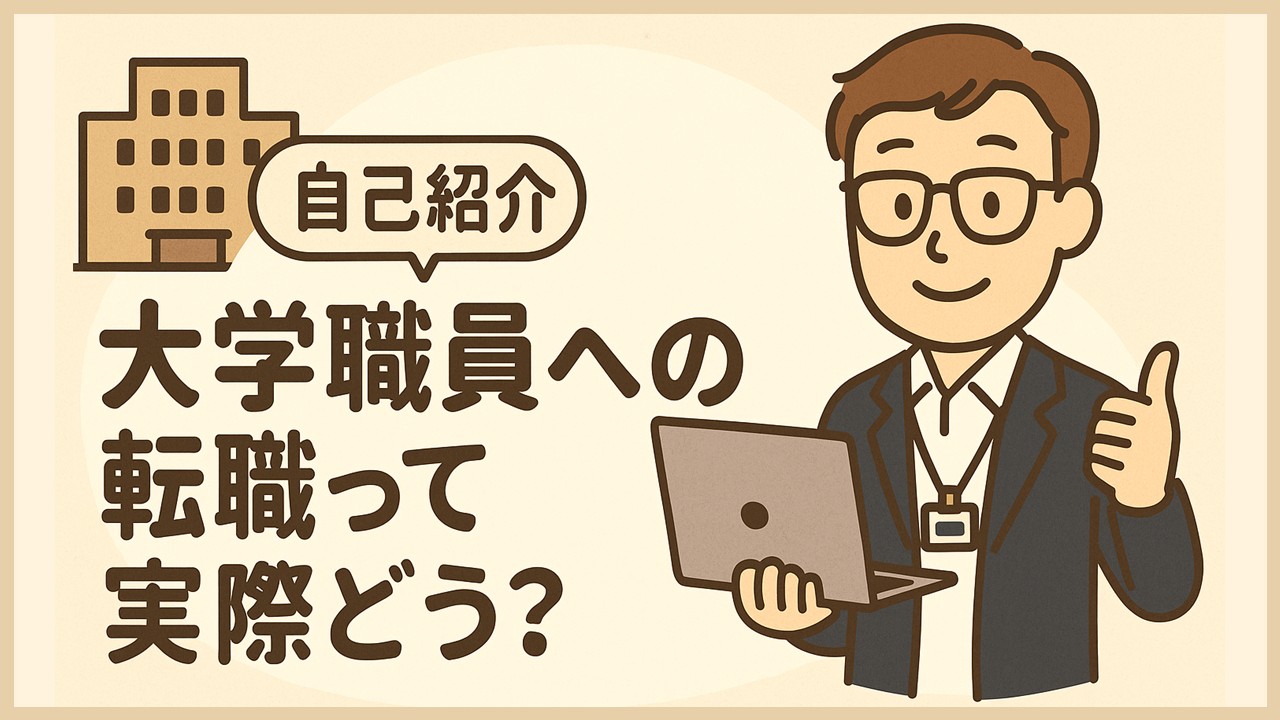大学職員の将来性は?現役職員による考察
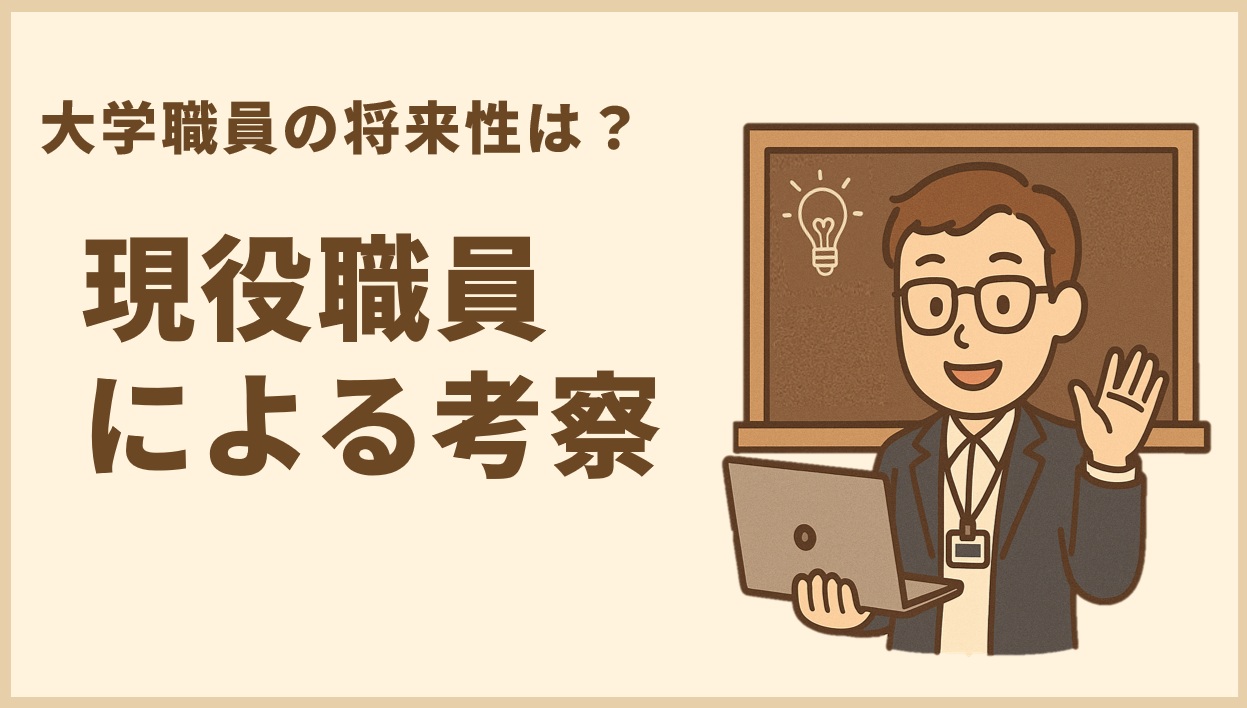

「大学職員って、この先も安定して働けるの?」
転職や就職を考えている人の多くは、この疑問を持っていることと思います。実際、転職活動中の私もそうでした。
大学職員は魅力的な要素が多い職業で、「安定してそう」というイメージも強いと思いますが、社会や教育を取り巻く環境は大きく変化しています。
この記事では、現役職員の視点から、大学職員の将来性とこれから求められるスキルや働き方について深掘りします。
まだ「安定」だけど、変化の波は確実に来ている
大学職員は、民間企業と比べて倒産リスクが低く、残業も少なめ。福利厚生も整っていることが多く、育児や家庭との両立がしやすい職種です。この「安定感」も、多くの人にとって魅力の一つだと思います。
しかし、近年の大学を取り巻く環境を見ると、この安定が永遠に続くわけではないことがわかります。
- 18歳人口の減少
少子化の影響で大学進学可能年齢の人口は減り続けており、文部科学省の推計によれば、2040年には18歳人口は100万人を切る見込みです。地方の大学ではすでに定員割れが深刻化しており、運営が厳しくなるケースも増えています。 - 競争の激化
少子化に伴い、学生獲得競争は激しさを増しています。オープンキャンパスや広報戦略、国際交流など、従来以上にマーケティング的な視点が必要になっています。 - 財政状況の厳しさ
国公立大学でも運営費交付金は年々減少傾向。私立大学も授業料収入に頼る構造のままで、経営の多角化や効率化が急務です。
最近の例では、東工大と医科歯科大の統合による「東京科学大学」の設立や、恵泉女学園大学や京都ノートルダム女子大の閉校決定など、有力大学における統廃合や閉校もニュースになっています。
このような背景から、大学自体、将来の存続のために変化が求められるようになっているのは事実です。また、それに伴って大学職員の仕事も従来のような単なる「事務処理」から、「大学の生き残り戦略を支える役割」へと変化しつつあります。
大学職員の仕事内容の変化
これまでの大学職員の仕事は、学生募集、授業運営、就職支援、総務・経理などの「事務作業」が中心でした。しかし今後は、業務改革や新しい企画立案が増えていくと思われます。
- 国際化対応
海外大学との連携協定、留学生対応、英語での事務手続きなど、語学力が求められる場面の増加。 - デジタル化・DX推進
紙文化からの脱却、学生ポータルの改善、業務の自動化など、ITスキルを活かした業務の増加。 - マーケティング・広報の強化
SNS運用、動画制作、留学生獲得のための海外展開など、広報手法の多様化。 - 産学連携・地域連携
企業や自治体と共同プロジェクトを進めるケースの増加。
私自身、今でも英語を使用する機会は日常的にありますし、ITスキルを使って電子化や自動化を進める仕事に取り組んでいたりしますので、既に業務内容は変化してきている状況だと言って良いと思います。
カギは「スキルのアップデート」
これまで述べてきた内容からすると、従来式の大学職員という観点では、残念ながら安定性は下がっていくといって良いでしょう。ただし、スキルに少し変化を加えるだけで、個人としての将来性は十分に高められると思っています。特に重要と考えているのは以下のスキルです。
- 英語力・外国語運用能力
これまでも重要でしたが、国際化が進む中で、英語でのメール対応や会議参加の頻度はより高くなっています。大学によってはTOEICやTOEFL、IELTSなどの英語能力試験のスコアが職員においても求められるケースは増えています。 - ITスキル・DX推進力
Word, Excel, PowerpointといったOffice系のツールはもちろん、Power BI、Power Automateなどのノーコードツールや、ChatGPT、Gemini、Copilotなどの生成AIなどのスキルも求められる(というより、あると活躍できる)と思います。 - プロジェクトマネジメント能力
部署横断のプロジェクトや外部との連携をまとめ上げる力もより求められることになると思います。
ただ、特に転職を考えている人であればこう思ったのではないでしょうか?
「え、そんなの今の会社でもうやってるじゃん。」
と。
そうなんです。大学職員の業務は、あえて悪い言い方をすると、世の中よりも1周か2周くらい遅れているんです。遅れ具合を表現するためにちょっと脱線しますが、例えば未だにFAXを使っていたりします。
なので、転職者はこれまでに培ったビジネススキルを大学職員に持ってくれば十分に将来的な活躍もできると思います。(大学が潰れさえしなければ)
まとめ:大学職員の未来は「安定+変化対応力」
まとめると、大学はまだまだ一定の安定性を保ちつつも、変化に対応していくことが必要であり、職員の働き方としても「変化に対応できる人」が生き残っていく時代になっていくと私は考えています。
というか、むしろそうやって変わっていくことによって、よりよい教育環境をつくっていかないといけないのだと思っています。
とはいえ、その変化は民間企業でバリバリビジネスをやっている人からすると既に当たり前のことだったりもするので、転職を考えている人にとってはチャンスです。
今回の記事を読んで、大学職員への転職に関して少しでも前向きになった人がいてくれたら嬉しいです。